オンラインセミナー「発達障害の強みを生かす教育法」

幼児教室ひまわりの熊野です。
「発達障害の強みを生かす教育法」というセミナーの2021年開催のご案内です。講師はNPO法人国際臨床保育研究所の勝山結夢先生です。
こちらのオンラインセミナーは、2020年1月16日に大阪会場で、2月13日に東京会場で開催されたセミナーを、オンラインで学べるように塾長の熊野が作成したビデオ講座です。
新型コロナウイルス拡大の状況にあたり、2021年はオンラインのみでの開催となります。
こちらのコースは、2020年は会場、オンライン合計で約200名の保護者の方が受講されました。
受講された方の生のアンケートを教室のブログで紹介しています。以下からご覧いただけます。
2020年2月13日開催(東京会場)の様子、受講者アンケート
2020年1月16日開催(大阪会場)の様子、受講者アンケート
上記のページの体験談にも書いていますが、受講者の方からは以下のような学びや感想が届いています。
- 「やるべきこと、方向性が見えて確信できた」
- 「学術的な理論面を説明してくれるので納得でき、行動に移せる」
- 「具体的な事例があって分かりやすかった」
- 「教育方針を見直すことができ、自信をもつことができた」
- 「わが子の将来への希望が持てた」
- 「安心できた、前向きになれた」
- 「日常生活に添っての話だったので実践しやすい」
- 「親の言葉がけの大切さを痛感した」
- 「今までは真逆のことをやっていたのではっとした」
発達障害のお子さんをお持ちの親御さんにとっては、とても学びの多い内容だと思います。
さて私たちの教室の発達障害に関する活動を、このページで初めてご覧になられる方もおられると思います。
ですから、こちらのページにも私たちが発達障害についてどのようにとらえているかをまとめています。よろしければ、ご参考になさってください。
以下でオンラインセミナーについてご紹介させていただきます。
私たちが発達障害の知育講座を始めたきっかけ
幼児教室ひまわりには、「発達障害(ADHD、自閉症スペクトラムなど)のお子さんの能力をどうすれば伸ばせるのかを教えてほしい」という要望がたくさん寄せられています。
私自身、こういう仕事をしていますので、もちろん発達障害のお子さんの知育に関して学んでいますし、知識を持っています。
大阪大学医学部でも小児科の学問として、小児の発達や児童心理、自閉症、ADHDなどについて、医学的な視点からも学んでいます。医者ですから、当然、薬についての専門的知識もあります。
しかし、私の社会のなかでの活動は、知育のプロであり、発達障害の専門家ではありません。ですから、そこに関しては専用の講座を設けていませんでした。
ただ、発達障害のお子さんの能力をどうやって引き出していけばよいのかは、しっかりとした情報をお伝えしたいという気持ちがありました。
ですから、私は「この先生なら安心して一緒にやっていける」という先生を全国各地で探していました。
今回、私が信頼できる素晴らしい先生との提携が決まりましたので、幼児教室ひまわりで講座を開催して頂くことになりました。
勝山結夢先生のご紹介

お話をしていただくのは、NPO法人国際臨床保育研究所研究員の勝山結夢先生です。
なお、NPO法人国際臨床保育研究所は、もともと辻井正先生という方が創業されました。
創業者の辻井正先生は2016年にお亡くなりになられ、現在勝山結夢先生が公演活動をを引き継がれています。
勝山先生は全国各地の幼稚園、保育園、市町村を対象に、保育環境の指導をされています。
つまり、「プロ(=保育園や幼稚園の先生)に対して保育環境を指導する立場にある先生」という方です。
そんなとてもお忙しい先生なので、勝山先生のお話を聞けるのはとても貴重な機会だと言えます。
(しかもオンラインで学べるというのは、おそらく幼児教室ひまわりが唯一の場だと思います)
さて、こちらのセミナーをご案内させていただく前に、まずは私の教室では発達障害についてどのようにとらえているのかをお話させてください。
そして、私の教室の考え方に関して共感できるようなら、ぜひ学んでみてくだされば嬉しいです。
幼児教室ひまわりの発達障害に関する考え方
まず大前提として、私は発達障害のことを、「障害=悪いこと、ハンデ」だとは考えていません。
ましてや、それが「病名」だとも、全く考えていません。
そもそも、グレーゾーンも含めて、発達障害の傾向にあるお子さんは6%ほどいると言われています。つまり、約16人に1人という計算になります。
私たちが子供の頃も、「ちょっと落ち着きがない子」「マイペースな子」がクラスに1人か2人くらい、いたと思います。
ちなみに、その1人が私熊野です(笑)
私自身も少し落ち着きがない傾向にありますので、私も今の時代であれば、「発達障害」という病名が付けられた可能性もあります。
そして、左利きの子の割合が約8%ですから、割合で言えばあまり変わりません。
これだけ高い確率でいるお子さんなのに、そこに障害という烙印を押すこと自体が、どうかしているのではないかと思います。
では、なぜ発達障害という名前を付けるのか。
その理由は、「日本の学校教育の目的が、社会に従順に適応できる人を教育する」ということにあるからです。
言われたらきちんと指示に従って、じっと座って授業を聞けて、嫌なことも我慢してできる・・・こんな生徒さんが評価されるのです。
発達障害のお子さんは、ここに上手に適応できないゆえに、「障害」という烙印を押されてしまうのです。困ったものですね・・・。
では、こういう状況に対して、私たちはどう考えればよいのでしょうか?
「障害」という月の裏面をご存知ですか?

発達障害のお子さんの知育を考えることは、月を見ることに少し似ています。
「真剣な話なので、月だなんて、ふざけないでください」と思われるかもしれませんが、私はこれが一番分かりやすいたとえ話だと思います。
月は表面しか見えません。決して裏面が見えないことは、多くの方がご存じだと思います。
病院とか療育の世界では、「この月の表面」しか見せてくれないのです。
月の表面だけを見て、「これは障害だ」と言っているのです。
でも、そこには裏面があり、そこを私たちは見る必要があるのです。
例を出すと分かりやすいので、1つ例を出しましょう。
たとえば、発達障害の1つにADHDという病名があります。
ここでは、敢えて私は「病名」と書きましたが、これは小児科の先生がそのように付けているだけです。
私は全然、それが病気だとは思っていません。
そもそも、社会の最前線で活躍しているADHDの人(勝間和代さん、黒柳徹子さん、アップルのスティーブジョブスさんなど)がたくさんいるのに、それを病気だというのは失礼な話だと思います。
でも、この「病名として付ける」ということがとても深刻なところなのです。
なぜなら、ネガティブな部分だけをとらえていて、親御さんが本質を見られなくなってしまい、混乱してしまうからです。
ADHDのお子さんは、「多動性」「衝動性」「不注意」という3つの特徴があります。(病院では特徴と言わずに、症状と呼びます)
たしかに、日本の学校のなかで、「社会に従順に適応できる人を教育する」という目的の中では、この3つの特徴が弊害になるのは事実だといえます。
これは否めない状況ですし、場合によっては加配などの手助けも必要かもしれません。落ち着いて授業を聞けませんし、授業中に立ち歩いたり、うわの空なので、それは大変です。
でも、ADHDのお子さんの「多動性」「衝動性」「不注意」の裏にある「本当の強み」には、誰も触れてくれないのです。
月の表面ばかりを見て、本当に重要な裏面を見てくれないのです。
・月の表面:「多動性」「衝動性」「不注意」
・月の裏面は??
もしかすると、あなたもその裏面を知らずに、
「わが子はADHDなので、将来が不安」
「何度言っても、何度叱っても、聞いてくれない」
「勉強をするように言っても、すぐにそれを忘れて別のことをする」
という不安に駆られているかもしれません。
もしあなたが、そのような状況で悩んでおられるのなら、まずはADHDの月の裏面を知って下さい。
ADHDの月の裏面は、「次々にアイデアが出てくる」という特徴です。
どんどんアイデアが出てくるので、それに従って動いているのです。
そして、「現時点で一番楽しく、打ち込めること」に対して、取り組んでいるだけなのです。
また、目の前にそういうことがなくても、頭の中から空想の世界で、そういうアイデアがこみあげてくるんです。
だから当然ながら落ち着きはありませんし、面白くなかったら授業にも集中できないのは当たり前なのです。
もし、あなたがそんな状況なのであれば、そうなるのは当たり前だと思いませんか?
どんどんアイデアがわいてくる、楽しそうなことが思い浮かぶのに、机について勉強なんてしてられませんよね。
このように発達障害の月の裏面が見えれば、おそらくあなたは、発達障害をハンデだとは思わなくなると思います。
ここではADHDを例に出しましたが、どんどん楽しいアイデアが出てくるなんて、とても素晴らしい状況だと言えますね。
学校の帰り道とかでも、「あっ!これ楽しそうだな」というアイデアが出てきたら、ランドセルを置き忘れてそれをやってしまうのです。
月の表面しか見えていなければ、「わが子は忘れ物が多くて、不注意だ。どうすればそれが治るのかな?先が思いやられる・・・」というネガティブな思考になってしまいます。
これに対して、月の裏面が見えていれば、
「また面白いアイデアが出てきて遊んでいるだな。ランドセルを置き忘れるくらい楽しいことだったんだな!」
というポジティブな視点でとらえることができるわけです。
まあ、親の側はだいぶ大変なのですが・・・それだけ大きな器を持った子供を育てているという気持ちで向き合うことが大切なのです。
ここはとても大切な部分なので、ぜひ押さえておいてください。
それでも、わが子の将来が心配。焦りとの戦い
わが子の強みをしっかりと伸ばしてあげたいという気持ちを抱えながらも、発達障害のお子さん、グレーゾーンのお子さんをお持ちの親御さんには目の前に試練が訪れます。
たとえば、こんな状況です。
- 「わが子はいつも同じおもちゃでばかり遊んでいて、親が与えるドリルには全然興味を示してくれない。」
- 「換気扇とかタイヤばかりを見ていて、普通の子が興味を示すおもちゃには目もくれない。」
- 「忘れ物が多かったり、持ち物を放り出して、そのまま遊びに行ってしまう。」
- 「親が言ったこともうわの空。叱っても全然効果がないし、顔色を伺おうともしない。」
- 「毎日すべきことを自主的にしない、塾の宿題も管理できない。」
- 「幼稚園でのお遊戯の時に、周囲に溶け込まず、わが子は砂いじりばかりをしている。」
- 「勉強するときは、きちんと机につかず、横になりながらやっている。」
こういう状況が目の前に訪れることが多いので、親御さんは不安になってしまいます。
「わが子が好きなことに打ち込ませてあげたいけど、このままでわが子の将来は大丈夫なのかな?」
「勉強もきちんとさせないと、中学受験も乗り越えられないし・・・。」
「毎日毎日、叱ってばかり。うちの子はどうなるのかな?」
このように焦ってしまうのです。
目の前の状況・・・つまり、他の子と様子が違ったり、他の子ができることが全然できなかったりする。そんな様子を見ると、とても不安になります。
その気持ちはよくわかります。
ただ、発達障害のお子さんの知育を考える際には、ここの戸惑いを上手に解決することがとても重要なのです。
なぜなら、
・わが子の好奇心を追求させて能力を伸ばしてあげたい
・でも、それで本当に大丈夫なのかなと不安を持っている
というのは、相反する気持ちだからです。
前者はアクセル、後者はブレーキになります。
アクセルを踏みながら、ブレーキをかけているような感じになってしまい、親子共にとてもしんどくなってしまいます。
だからこそ、ここで上手に、自信を持ってお子さんに関わることで、お子さんの将来が変わっていくといえます。
どのような理論をもとに、どういう方針を取ればよいのか・・・それを講座のなかで学術的な面と、実践的な面の両方から説明していきます。
これが、本セミナーの肝の部分となります。
会場で受講されたみなさま、この部分をしっかりと学ばれました。
その結果、お子さんへの接し方の迷いが減り、ずいぶんと楽になったとおっしゃっています。
オンライン講座の詳細について
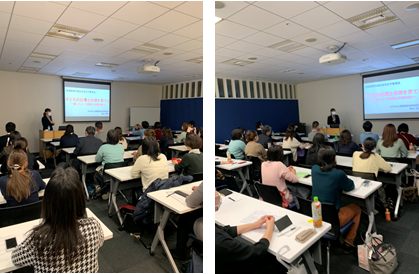
こちらのオンライン講座は、東京会場、大阪会場で開催された講座をそのまま収録したものではありません。
会場の講座と同等の学びを得られるように、塾長の熊野が作成したオンライン版専用講座となります。(東京会場の活動報告、大阪会場の活動報告)
オンライン講座にお申込みいただくと、専用のメンバーページをご案内します。そちらのメンバーページのなかで、ビデオを視聴しながら、学んでいただくことができます。
パソコン、iPad、スマートフォンなど、ネットで動画を視聴できる環境があれば、全国(世界中)どこでも視聴して頂くことが可能です。クレジットカード決済が可能であれば、海外の方でもお申込みいただくことができます。
また、メンバーページの視聴の期限などはございません(幼児教室ひまわりを運営している限りは視聴可能です)。ですから、メンバーページを視聴することで、いつでも内容を見直していただくことができます。
なお、会場では勝山先生に対しての質疑応答の時間がございましたが、オンライン版では勝山先生への質問はできません。その代わりとして、オンライン版には熊野と勝山先生の質疑応答の対談音声が付属しています。
以下、オンラインビデオ講座の詳細となります。ご確認のうえ、お申込みください。
なお、こちらのオンライン講座はお申込み期間などの制限はございません。このページが表示されている間は、いつでもお申込みして頂くことが可能です。
| オンライン講座名 | 発達障害の強みを生かす教育法 |
|---|---|
| 講師 | 幼児教室ひまわり塾長 熊野貴文 NPO法人国際臨床保育研究所 勝山結夢先生 |
| 対象者 | ・発達障害のわが子の才能を伸ばしてあげ、社会で活躍させてあげたい方 ・発達障害の子供の教育方針についてしっかりと固めたい方 ・発達障害と診断されていなくても、少し変わったわが子の知育法を学びたい方 ・幼児教室ひまわりの発達障害に対する方針に共感できる方 ※お子さんの対象年齢について 発達障害のお子さんとの接し方については、年齢に関わらず共通した内容をお伝えしていきます。主に小学生くらいまでのお子さんの内容となります。ただし、発達障害をお持ちのお子さんは、発達に個人差がありますので、明確には「対象年齢が何歳」というくくりはありません。基本的にはお子さんが何歳であったとしても、役に立つ内容です。 |
| 受講費 | 25,000円(税込 27,500円) |
| お支払方法 | ・銀行振込 ・クレジットカード決済(オンラインでの決済) |
| 講座カリキュラム | 第1部 これからの時代の変化と、生き抜く力について ・これからの時代がどのように変わっていくか?世界の動きについて ・変化の激しいIT化、AIの時代に必要とされる人材と発達障害の強み ・OECD2030の教育方針と、これからの時代を生き抜く3つの力 ・なぜ発達障害のお子さんが力を発揮できるのか? ・発達障害のお子さんの強みをこれからの時代にマッチさせる 第2部 発達障害のお子さんの自己肯定感を培う秘訣 ・自立と自律の違いを知り、自己肯定感を培う ・偽物の自尊心、本物の自尊心 ・自分で判断させ、考える力を培う手順 ・発達障害のお子さんに対するNG事項 第3部 発達障害のお子さんの学びを最大化する環境づくり ・学びの根源的エネルギーとなる2つの要素 ・表面的な学びと本質的な学びを分けるもの ・学びをやめてしまう脳のスイッチ ・好奇心を追求した先には、一体何があるのか? 第4部 熊野×勝山 特別対談 ・わが子が自律を意識するための接し方のコツ ・発達障害のお子さんをお持ちの親御さんがよく見落としていること ・自己肯定感を下げない上手な叱り方、促し方 ※セミナー動画の時間は、全部で約90分となります。 |
オンライン講座のお申し込みはこちらから
ここまで色々なことをお伝えしましたが、私がお伝えした内容があなたの希望につながればとても嬉しいです。
発達障害のお子さんには突出した強みがあるからこそ、それが日本の学校に上手に適応できない原因になっているのです。
その強みを生かすことができるかどうかは、親御さんにかかっていると言っても過言ではありません。
まずは、「わが子のせっかくの強みを弱みだと勘違いしない」ということから始めてみてください。
そして、実際にわが子にどのように接していけばよいのかをしっかり身につけたい方は、ぜひ今回のオンラインビデオ講座を受講してみてください。
お申し込みは以下から手続きできますので、決済方法に合わせてクリックしてください。
(詳細ページが表示されます。)
こちらのセミナーの受付は完全終了しました。多くの方からのお申し込みをいただき、誠にありがとうございました。
受付期間:2021年4月18日12時~2021年4月20日24時(※締切)
(次回の開催の予定は現時点ではございません。)
特定商取引法に基づく表記
販売業者
イノベーションシステム株式会社(屋号:幼児教室ひまわり)
運営統括責任者
熊野貴文
住所
大阪府大阪市淀川区西中島4-2-6
NLC2号館7階
電話番号
06-6307-1112
(受付時間:9:00~18:00、土日祝日を除く)
メールアドレス
info@himawari-child.com
販売価格
25,000円(税込27,500円)
商品代金以外の必要料金
商品代金以外に必要な料金はありません。
商品の引渡し時期
クレジットカード決済の場合:お申込み手続き後5日以内
銀行振込の場合:当社指定の口座に着金後5日以内
商品の引渡し方法
Eメールにて、メンバーページのURLをご案内します。
お支払い方法
銀行振込・クレジットカード払い
返品・交換キャンセル等
商品お申し込み後のキャンセル、返金などは受け付けておりません。