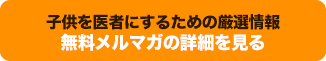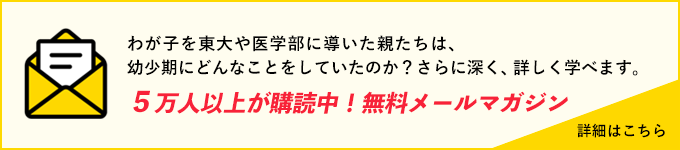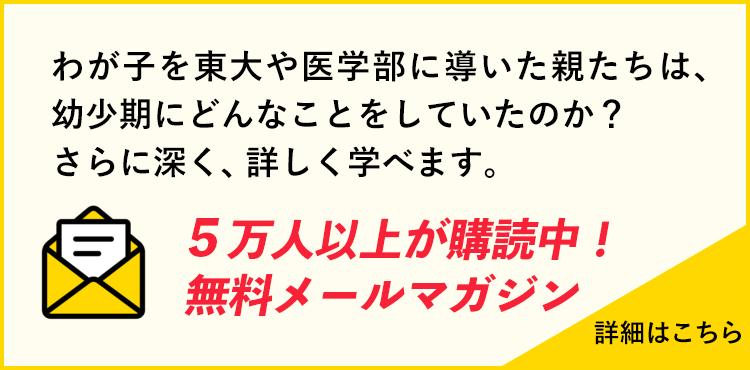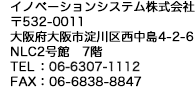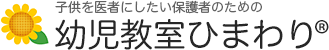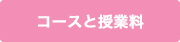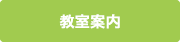子供の非認知能力を鍛える教育法 幼児、小学生の時にすべきこと
執筆者:熊野貴文(幼児教室ひまわり塾長)
最終更新日 2022年10月02日
数値では測り知れない「非認知能力」の教育はどうすれば良いのか?
これまで1万人以上の保護者を指導してきた私の経験をもとに、「子供の非認知能力を鍛える教育法や幼児、小学生の時にすべきこと」についてご紹介いたします。
最近、保護者の方からよせられるご質問で多いのは、
「発想力や創造力を鍛える必要があると思うのですが、どう教育すればよいのでしょうか?」という内容です。
発想力や創造力。
実は小学生の国語や算数の能力と違い、数値では評価されないんですね。
他にも、意欲、忍耐力、自制心、理解の速さ、社会性、好奇心など・・・
数値では測り知れない能力が、たくさんあると思います。
こんな数値で測れない能力のことを「非認知能力」と言います。
そして非認知能力を鍛えることが、ここ最近の幼児教育の世界ではとても大切だと言われています。
そこで今回の記事のなかでは、この非認知能力について考えます。
それでは、始めていきましょう。
非認知能力と認知能力のバランス

ここ最近の教育メソッドのなかには、非認知能力を鍛えることを目的としたものが多いです。
たとえばこんな感じの広告をよく見ると思います。
- このメソッドはお子さんの発想力をぐんぐん高めます
- 意欲を引き出し、勉強が好きになる最新のシステムによる教材
- このカリキュラムを受けることで、頭が良くなり、理解が早まります
発想力、意欲、理解が早くなる・・・。
最近の幼児教育のメソッドは、このような非認知能力に対してかなりのフォーカスを置いています。
そういう意味では、私がやっていた公文式などは結構地味ですね。
算数とか、国語とか、英語とか、教科ごとしかないですからね。
ある意味、古いのかもしれません。
もちろんこういう非認知能力ですが、ぜひ鍛えていくべきだと思います。
お子さんの地頭を良くするので、プラスに働くと考えられます。
ただ、1つだけ誤解したくないのは、
「4歳以降は、非認知能力だけでなく認知能力も意識することが大切」
だということです。

3歳くらいまでは、算数や国語など、認知能力を評価する機会は少ないものです。
ですから、「非認知能力100%」という教育方針で良いと思います。
逆にあまりにも小さな時期に、算数とか国語を詰め込んでいくと、勉強嫌いになる可能性もあります。
そして、4歳くらいになってくると、早い子であればお勉強を始めます。
算数や国語に少しずつ取り掛かり、足し算ができたり、文字が書けたりなど、結果が出てきます。
この時点になると、保護者ごとに教育方針が分かれてきます。
・認知能力も必要だと意識する人
・非認知能力100%という人
年中から年長さんのこの時期はお子さんの発達にも個人差があり、どちらが適切かは分かりません。
お子さんの興味を見ながら少しずつ勉強を取り入れていき、認知能力も身につけていきます。
ですから、この時期は「認知能力も30%くらい意識する」というスタンスくらいがバランスが取れていると思います。
少しずつ勉強を取り入れていって、学習習慣を形成していきます。
さて、問題は6歳以降です。
年長さんから小学1年生以降ですね。
ここで非認知能力だけを意識し、認知能力を無視しているとかなり遅れをとってしまいます。
「国語や算数はできないけど、発想力はあるから大丈夫よ。いつかは能力を発揮するはず・・・」
という感じですね。
つまり、「テストは悪いけど、頭は良い子」ということですね。
ただ、これは楽観的すぎます。
非認知能力だけはなく、認知能力もしっかりと見ていく必要があります。
小学生になると、授業やテストが始まり、日常生活に勉強が組み込まれてきます。
認知能力も意識して勉強させないともう追いつけなくなってきます。
トップクラスから離脱するんです。
ですから、非認知能力と認知能力の両方を鍛える必要があります。
つまりまとめると、
・3歳までは非認知能力100%
・4歳、5歳は認知能力30%
・6歳以降(小学生)は両方を鍛えていく
というのが良いと思います。
これが私自身が受けてきた教育、そして多くの灘中学の生徒たちの共通点だと言えます。
また、勉強をしたからといって、非認知能力が高まらないとは限りません。
むしろその逆だと言えます。
特に小学生の算数の問題を解くためには空間を把握する想像力が必要ですし、国語の問題のなかでは話の組み立てを理解したり、登場人物の気持ちを理解しないといけません。
色々と頭を使って、様々な能力を使って問題を解かないといけないのです。
つまり、勉強こそがおこさんの非認知能力を鍛えるためのよい機会にもなるわけですね。
【参考情報】非認知能力とは?SELとは?
非認知能力を鍛える第1歩
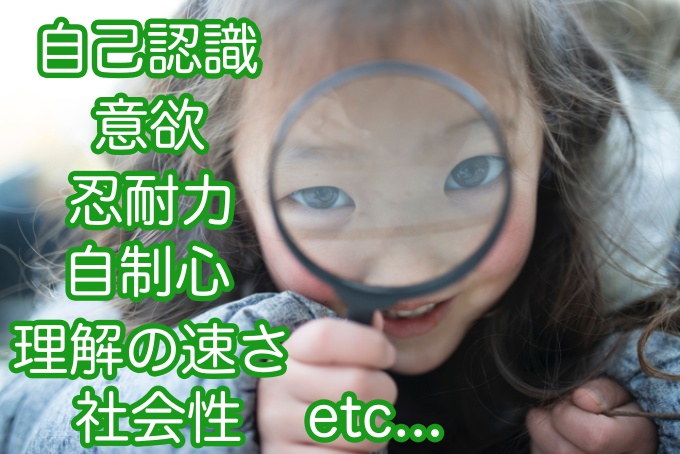
さて、この「非認知能力」ですが、お子さんのベースとなってきます。
ですから、お子さんの生涯にわたり、親が教育していく必要があります。
「認知能力=各教科の勉強」
と併せて、親が常に意識して鍛えていってあげないといけません。
それでは、具体的に何をすれば非認知能力を鍛えられるのか。
その第1歩は、非認知能力にはどんな要素があるのかを知る事です。
■ 自己認識
自分のことをどういう存在として捉えているのかという根底の考え方
■ 意欲
目標を成し遂げるために、どれくらいの熱意を持っているのか
■ 忍耐力
つらいことにも耐え抜き、頑張る力
■ 自制心
冷静になり、長期的な視点で考え、感情をコントロールする力
■ 理解の速さ
物事の本質を掴み、理解する能力
■ 社会性
周囲の人の気持ちを考えて、気配りする優しい心
ルールに従って秩序を守ること
■ 精神面の回復力
嫌なことが起こった際にも、くじけずにもう一度再起する力
■ 創造力
新しいものを発想し、作り出す力
■ 好奇心
見たことない世界に興味を抱き、取り組もうとするチャレンジ精神
ここで挙げたのはその一例ですが、非認知能力と一言に言ってもかなり多くの要素があります。
ただ漠然と捉えるのではなく、各要素に分けて考えていくとその鍛え方が見えてきますね。
まずは、あなたのお子さんの状況を、各能力に関して1つずつチェックしてみること。
そして各要素について鍛えるために、何をすれば良いのかを考えることが、非認知能力を鍛える第1歩になると思います。
【参考情報】非認知スキル向上プログラム
幼児教室ひまわりでは、お子さまの脳を鍛える具体的な方法や難関中学に合格するための勉強法などを、オンライン講座やメールマガジンで公開しています。
もっと深く学びたいという方は、ぜひ私たちのメールマガジンにご登録ください。
この記事を読まれた方にオススメのコラム