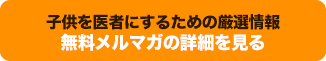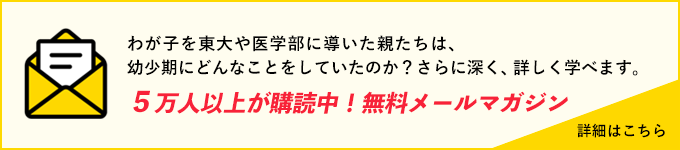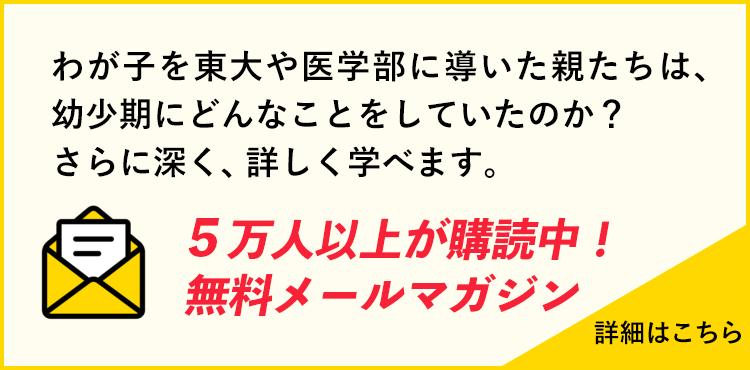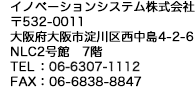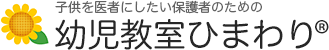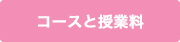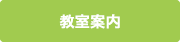子供の人間関係に、親がどう干渉すべきか?
執筆者:熊野貴文(幼児教室ひまわり塾長)
最終更新日 2022年10月02日
「子どもの人間関係について、親がどこまで見ていけば良いのか?」と悩まれる親御さんも多いですね。
幼児教室ひまわり塾長として、これまで1万人以上の保護者の方を指導してきた私の経験から、「子供の人間関係に親がどう干渉していくか」について解説いたします。
最近増えてきた課題として、「子供の人間関係をどうしていくか?」というテーマが挙げられます。
最初に私が指導させて頂いている内海さんからのご質問を紹介します。
------------------------------
■ 内海さんからのご質問
------------------------------
熊野先生、こんにちは。
先生のご指導を受けていると、子供の教育環境ってすごく大事なんだと痛感します。
そこでひとつ疑問があるのですが・・・
親は子供の人間関係に対して、どれくらい関われば良いのですか?
また、あまりお付き合いしたくない子供と仲良くなった場合は、親はどう対応すればよいでしょうか?
アドバイスを頂ければ幸いです。
こんなご質問が届きました。
「朱に交われば赤くなる」と言いますように、子供の学習習慣や思考習慣に関して、周囲の子供の影響は大きいです。
子供を医者にしたい親の立場として、やはり賢い子どもと仲良くなって良い影響を受けたいものですね。
お子さんの人間関係について考えていく際に、最初に考えておきたいのは、「類は友を呼ぶ」ということです。
まずはここから、しっかりと抑えていきましょう。
【参考情報】子どもたちにおける友人関係の変化
類は友を呼ぶ

「類は友を呼ぶ」ということわざがあります。
中学受験の範囲でもあるので、国語の問題でよく出題されます。
「類は類を呼ぶ」と勘違いしている人がいますが、これは間違いです。
「類は友を呼ぶ」というのが、正しい表現です。
このことわざは、「似た者どうしが仲良くなる」という意味なのですが・・・これは当然のことですね。
自分と考え方が極端に違ったり、価値観がずれている人とはなかなか仲良くなれないものです。
・健康に関する価値観
・お金に関する価値観
・仕事に関する価値観
・教育に関する価値観
などなど。いろいろな価値観があるのですが、考え方が合わない人とはどうしても居心地が悪くなるんです。
短期的にはよかったとしても、長期的にはしんどいわけですね。
そして、この現象は子供の人間関係においても同じです。
つまり、「あなたのお子さんの周囲には、似たような子が集まってくる」という状況になるわけですね。
似ていない子と一緒にいると、お互いに居心地が悪くなるんです。
これは考えれば当たり前なのですが、大切なのはここからです。
1つ考えてみてください。
「あなたのお子さんの周囲には、どういう子に集まって欲しいですか?」
この問いに答えることが、あなたのお子さんの周囲の人間関係を良くするヒントになるのです。

私の教室に来ている方にも同じ質問をよくしています。
するとこういう答えが返ってきます。
・勉強ができる子
・頑張って挑戦していく子
・明るく前向きな子
・優しくて思いやりがある子
保護者のみなさん、わが子にはこういう子とお付き合いして欲しいわけです。
そして、ここで挙げた要素には共通点があるといえます。
それは、「自己肯定感が高い」ということです。
自己肯定感というのは、「自分の存在に誇りを持ち、能力にも自信を持っていること」という意味なのですが・・・自己肯定感が高いことによって、どんなことでも成し遂げ、未来を切り開いていけるんですね。
そして、こういうことが言えます。
「自己肯定感が高い子が周囲に集まる環境を作りたいなら、あなたのお子さんもそうなる必要がある」
というわけですね。
「類は友を呼ぶ」からです。
「お前なら絶対にできるよ」「難しいことにチャレンジして、本当にがんばっているね」「生まれてきてくれてありがとう」・・・
こういう言葉をかけてあげて、子供の自己肯定感を高めること。
そうすることによって、お子さんの周囲には似たような子が集まってきます。
自己肯定感が高い子どうしで、より高い目標に向けてがんばり、切磋琢磨していく関係ができます。
ですから、子供の人間関係について考える際に、あなたが最初に意識すべきことは、「まずは子供の自己肯定感を高める」ということになります。
ここを十分に意識したうえで、「どうやって子供の人間関係を、良い友達で囲んであげるか」ということを考えていくわけです。
それでは具体的な方法についてお伝えしていきましょう。
【参考情報】安定した居場所が自己肯定感に与える影響
お子さんが幼稚園までの場合

お子さんがまだ小さなうちは、とてもシンプルだといえます。
なぜなら、「親同士の人間関係がそのまま子供の人間関係になる」からです。
仲の良いママ友と過ごすときに子供が一緒に来るわけですから、そこの子供と仲良くなります。
つまり、ママ友選びが大切ですね。
私は男なので、ママ友選びについてはちょっと専門外なのですが・・・
私の教室の女性講師(自分の子供を医者にした先生)の言葉をお借りすると、「子供をどういう子に育てたいか」という方向性が一致する親御さんを選ぶことが大切だといえます。
そのためには、あなた自身の方針もしっかりと言葉に表しておくことが大切だと言えますね。
自分の方向性が定まっていないのに、「相手とそれが一致しているか」が分かるわけないですから。
それでは、お子さんが小学校以降は、どうすればよいのでしょうか?
【参考情報】幼児を持つ母親の仲問関係と育児困難感
お子さんが小学校以降の場合

お子さんが小学校以降になると、小学校でのお付き合いがあるので親が関与しにくくなります。
「あの子とあまり仲良くしたらダメ」と言ったとしても、結局判断するのはお子さんですし、お子さんの自由な判断を奪うことにもなってしまいます。
ここでの対処法については、幼児教室ひまわりの主任講師の藤井先生の方法がとても器用でスムーズなのでご紹介させていただきますね。
オススメの方法としては、
・家に遊びに来ても良い子
・家に遊びに来てはいけない子(学校だけでお付き合いする子)
というように区別することです。
この部分に関しては、親が決めることができるわけです。
家に遊びに来るとなると、親のフィルターが1枚入りますので、「親が仲良くなって欲しいお友達」とだけ遊ばせることができます。
学校でのお付き合いに関しては、お子さんの判断に任せる。
そのうえで、家に遊びに来るという段階で選別していくわけですね。
家に来て一緒に遊べば、その子とさらに仲良くなり、お子さんの周囲の人間関係を「親がお付き合いしてほしい子」で固めていくことができるのです。
とても効果的なテクニックですから、ぜひ使ってみてください。
最後に1つ。
根本的なご質問にお答えします。
それは、「子供の人間関係を、親がコントロールして良いのか?」ということについてです。
この答えですが・・・「もちろん、子供が付き合う相手を親が選び誘導しても良い」と、私は思います。
これはコントロールとは全然違います。
お子さんが誰とお付き合いするのか、誰と仲良くなるのか。これについては、お子さんが自分で判断することになります。(自主性を尊重してあげてください)
しかし、その選択肢については、できるだけ親御さんが用意してあげるのが良いと思います。
なぜなら、お子さんが毎日を過ごすために良い環境を作ってあげることは、親の重要な役割だからです。
子供の心は純粋ですから、
・後ろ向きな生き方をしている子
・思いやりの無い意地悪な子
・自己肯定感が低い子
・きちんと勉強をしない子
このような子供の中に生きると、「それをあたり前」と思ってしまいます。
知らない間に真似してしまい、悪影響を受けてしまうんです。
ですから、そこを守ってあげるのがとても大切ですね。
この記事でお伝えしたポイントを意識し、ぜひお子さんの周囲を素晴らしい人間関係で包んであげて頂ければと思います。
【参考情報】仲間関係のなかで育つ子どもの社会性
こちらのページでは、「子供の人間関係に対して、親がどう干渉していくべきか」というテーマについてお話しましたが、幼児教室ひまわりでは、お子さまの脳を鍛える具体的な方法や難関中学に合格するための勉強法などを、オンライン講座やメールマガジンで公開しています。
もっと深く学びたいという方は、ぜひ私たちのメールマガジンにご登録ください。
この記事を読まれた方にオススメのコラム