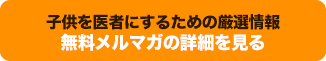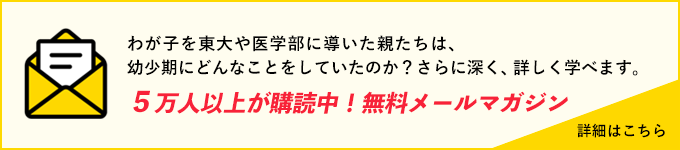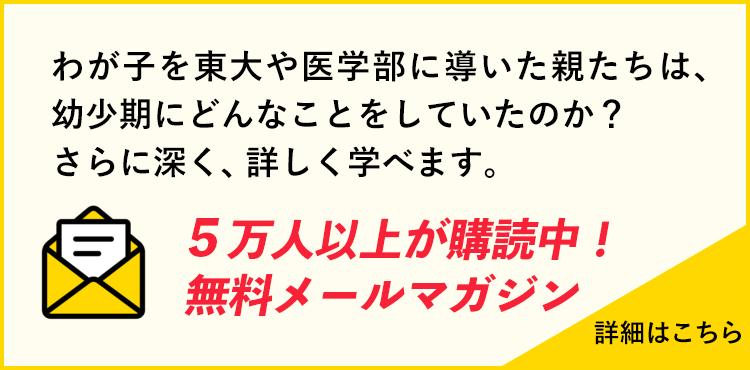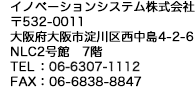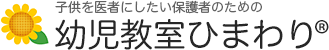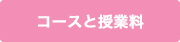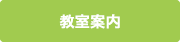中学受験には習い事が障害になるのか?我が子が灘中学に合格した親の考え方
執筆者:熊野貴文(幼児教室ひまわり塾長)
最終更新日 2022年11月04日
中学受験の勉強と習い事のバランスについて、灘中学、大阪大学医学部に合格した私と、お子さんを灘中学合格へと導いた当教室の上田先生と柴田先生の教育をもとにご紹介いたします。

中学受験を目指す場合、「習い事」について、悩まれることが多くなります。
その悩みとは主に、
・中学受験の勉強と習い事が両立できるのか?
・習い事が中学受験の勉強の障害にならないのか?
という点です。
さらには、もし習い事をする場合は、習い事をどう始めて、どう終わるか?という悩みもあります。
中学受験を目指す場合は、小学校3年生か4年生くらいから進学塾に通い始めます。
中学受験の勉強と習い事のバランスをどうすれば良いか?
多くの親御さんが悩まれております。
そこでこちらのページでは、
・中学受験に習い事が障害になるか?
・習い事と中学受験は両立できるか?
・習い事をどのように始めて
・習い事をどのように整理していくのか?
これらについて詳しく解説していきます。
中学受験に習い事が障害になるか?

中学受験と習い事の両立となると、多忙になりすぎることが懸念されます。
志望する中学の難易度や、塾のカリキュラムによって違いはありますが、学校と塾だけであれば、合間に余白の時間が生まれます。
塾や学校の宿題・課題を終えてもゆっくりできる日もあるかもしれません。
しかし中学受験の準備と習い事を並行していると、その余白すらなくなってしまう可能性がでてきます。
余白の時間がなくなってしまうことで、疲れを取る機会が減っていきます。
疲れが蓄積され続けると、睡眠にも悪影響を与えるケースも珍しくありません。
疲れすぎて睡眠不足に陥るようなことになってしまっては、習い事を継続することは中学受験への障害になってしまいかねないのです。
中学受験に挑む小学生にとって、睡眠不足は何よりも深刻な問題です。
頭が回らなくなるだけでなく、疲労からくる倦怠感などはモチベーションの低下にもつながりかねません。
普段は起こり得ないケアレスミスなどが連発しだすと、自己肯定感の低下を引き起こすことも考えられます。
習い事の内容次第では、必ずしも障害となるとはいい切れません。
しかし時間的余裕がなくなることや睡眠不足問題が起こるのであれば、習い事が障害となってしまう可能性は大いにあるでしょう。
習い事と中学受験は両立できるか?
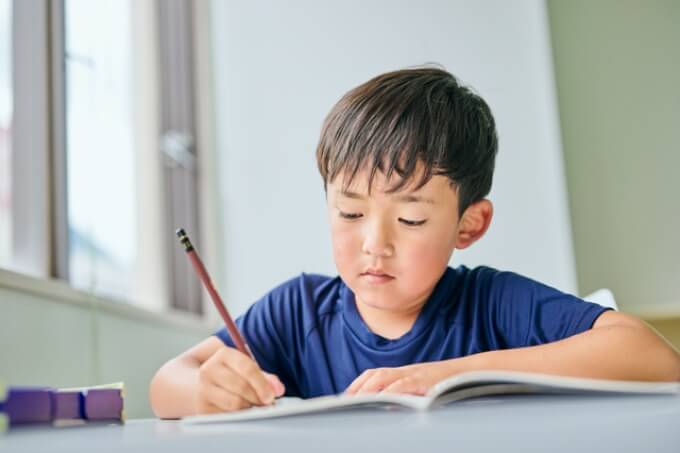
中学受験と習い事を並行させることは、非常にむずかしいことかもしれません。
しかしやり方次第では中学受験と習い事を両立させることは可能です。
中学受験と習い事を両立させられるかどうかのポイントを見てみましょう。
・習い事の回数が少ない、時間が短い
・日程や時間の調整がつけやすい
・習い事が楽しい、ストレス解消になっている
・習い事の先生が中学受験に理解がある
・子ども自身が両立させることに前向きである
これらのポイントをクリアできるのであれば、両立を考えてみてもいいかもしれません。
まずは習い事の数を厳選することからはじめてみましょう。
辞めるのか休会するのか、習い事へ行く回数を減らすのかなど、選択肢はさまざまです。
あくまでも中学受験の勉強を優先しながら、親子でしっかりと話し合い、両立できるラインを探すといいでしょう。
ポイントは、決して親が独断で決めてしまわず、必ず親子で納得が行く話し合いを行うことです。
親子で納得のいく結論が見つかれば、あとはトライアンドエラーを繰り返しながら調整をしていくのみです。
ムリが生じていると気がつけば、その都度考え、最善策を探していきましょう。
そうすることで、必ずしも習い事をすべて辞める必要はなくなるかもしれません。
習い事の始まり:「どんな習い事をするか?」よりも重要なこと

それでは次に、習い事の「始まり」についてお伝えします。
「賢い子に育てたい」「将来、医学部に導きたい」と考えている場合、
学習系の習い事をすれば良いというわけではありません。
将来、社会で活躍する大人になるためには、学力も重要ですが、
体力やコミュニケーション能力など、総合的な力も必要です。
ですので、学習系、運動系、芸術系の3つのタイプの習い事を考えていくようにします。
・学習系:公文式、そろばん
・運動系:水泳、体操、
・芸術系:ピアノ、バイオリン、絵画
などですね。
このような習い事は、親御さんが主導となり、お子さまが幼児期の頃から通わせる場合が多いと思います。
ですので、この時まず考えるべきことは、「お子さまが楽しくなるように導く」ということです。
実は、「どんな習い事をするか?」というのはそこまで重要ではありません。
たとえば東大に合格した人たちの幼少期の習い事のアンケートをとると、
公文式をやっていた人もいれば、そろばんをやっていた人もいます。
水泳をしていた人もいれば、水泳をしていなかった人もいます。
ですので、「この習い事をすればトップレベルになれる」というものではありません。
重要視すべきことは、「習い事を楽しむ」ということです。
たとえば、ひまわりの講師上田先生は、ご長男を幼児期から体操教室に通わせました。
その目的は、「運動ができたら楽しい」ということを実感してもらいたかったからです。
上田先生は、ご自身が運動が苦手でだったこともあり、そのせいで学生時代が楽しめなかった部分がありました。
運動が得意であればあるほど、学生生活も楽しめますし、いろいろな世界を知ることができます。
そのような想いから、お子さまに対して、
・運動に苦手意識を持たせないように
・運動が楽しいと思えるように
運動系の習い事(体操教室)に通うようになりました。
結果、上田先生のご長男は運動も得意になり、灘中学に合格後は、ラグビー部の主将も務めるようになりました。
このように、幼児期から習い事を始める場合は、「楽しむ」ことを優先します。
学習系でも運動系でも芸術系でも考え方は同じです。
幼児期の子どもは、「楽しい」と思えるものは、夢中になり、努力をし続けるので、みるみる成長していきます。
ですので親御さんとしては、まずは気になる習い事はやってみて、「わが子が楽しめているか?」
面白くなさそうに見えたら、「どうやったら楽しめるか?」
そんな視点で接してあげることを心がけていきましょう。
【参考情報】早期教育について
習い事の終わり:習い事の辞め時は、子どもが自ら決められるように。

それでは次に、習い事の「終わり」について。
「習い事をいつ辞めるのか?」ということですね。
習い事の「終わり」についての理想は、子どもが自らの意思で決めるということです。
実際に私も、進学塾に通い始める時は、自分の意思で、それまで通っていた習い事を辞めました。
ひまわり講師の上田先生も柴田先生も、お二人ともご長男は灘中学に合格しているのですが、
お子さまの意思で、習い事を辞めたそうです。
では、このように、子ども自らの意思で習い事を辞め、
習い事から進学塾へスムーズに移行できるようになるためには、親御さんは何をすれば良いのか?
ポイントは次の2つです。
1.「勉強することが当たり前」という環境を作る
2.強引に全ての習い事を辞めさせようとしない
1つずつ解説します。
1.「勉強することが当たり前」という環境を作る

まずは、「勉強することが当たり前」という環境を作るようにします。
たとえば上田先生は、お子さまたちにそれをストレートに伝えていました。
上田先生はお子さまたちに、
「お父さんは家族のために仕事を頑張っている」
「私はあなたたちを育てることが仕事」
「あなたたちは勉強することが仕事」
というように、「勉強することが仕事であり、勉強することが当たり前である」という環境を作っていました。
もちろん強制ではなく、「勉強するから夢が叶う」ということを繰り返し体験させていました。
このように、お子さまたちが「勉強することが当たり前」という意識を持っていれば、
運動も頑張りますし、芸術も頑張りますが、最終的には必ず勉強も頑張る。
というメリハリをつけられるようになります。
ですので、勉強に集中しなければいけない受験期には、習い事を自ら調整(辞める)するという選択ができるようになります。
2.強引に全ての習い事を辞めさせようとしない

小学校中学年から進学塾に通い出したとしても、
親御さんから強引に、「中学受験の勉強に集中するために習い事を全て辞めるよ!」という伝え方をするのは
おすすめしません。
やはり、お子さまが反発する可能性もあり、それによって受験勉強に集中できなくなる恐れもあります。
ですので、できるだけ親子で話し合うようにします。
柴田先生のお子さまも体を動かすのが好きで、小学校時代はサッカースクールに通っていました。
このサッカーを、小学校5年生まで続けていました。
サッカーが気分転換になるということで、お子さまにとって、とても大事な時間だったからです。
柴田先生は、お子さまのその意思を尊重し、疲れている時は休ませるなど、
多少の調整は提案しましたが、強引に辞めさせるようなことはしませんでした。
習い事というのは、いきなりスパッと辞める必要はありません。
勉強が忙しくなれば、習い事の回数を少なくすれば良いですし、休んでも良いのです。
少しずつ勉強の時間を増やしていけば、うまく調整できるようになります。
柴田先生のお子さまも、その後は、灘中学を本格的に目指す時期になると、自然と勉強量が増えてきて、
自らサッカーを辞める決断をしたそうです。
このように、お子さまが自らの意思で習い事を辞める決断ができるように、
親御さんは環境を整えてあげることが、大切だと思います。
【参考情報】子どもの主体性を育む支援の在り方
子供の習い事は親がバランス調整する

以上、こちらのページでは、「習い事と中学受験は両立できるか?」についてお伝えしました。
子どものにいろいろな体験をさせるためにも、習い事はした方が良いと言えます。
ただ、中学受験をする場合は、両立は可能なのですが、状況や時期を見ながら整理していく必要がります。
習い事を始める時には、「どんな習い事をするか?」よりも、
「どうやって習い事を楽しませるか?」ということを意識しましょう。
習い事を辞める時(進学塾へ移行する時)は、子どもが自らの意思で決められるような環境を作ってあげます。
その際には、こちらの2つのポイントを意識すると良いでしょう。
1.「勉強することが当たり前」という環境を作る
2.強引に全ての習い事を 辞めさせようとしない
中学受験に挑戦する場合は、「いろいろなことを犠牲にして受験勉強に集中する」というイメージがありますが、やはりリフレッシュの時間も重要です。
進学塾以外の習い事などが、良いリフレッシュになることもあります。
習い事や受験勉強のバランスは、上手く親御さんが調整してあげましょう。
幼児教室ひまわりでは、お子さまの脳を鍛える具体的な方法や難関中学に合格するための勉強法などを、オンライン講座やメールマガジンで公開しています。
もっと深く学びたいという方は、ぜひ私たちのメールマガジンにご登録ください。
この記事を読まれた方にオススメのコラム